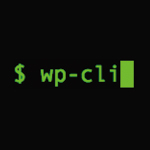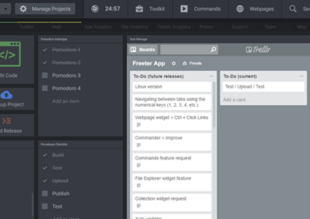concrete5を導入するなら、発注側も制作に関わると良いかもしれない。という話。
昨年に続き、今年もconcrete5のadvent calendarに参加させていただきます。
今年は東京ユーザーグループでもお世話になっている、遠藤さんの投稿「concrete5 5.7.5系のコマンドラインツールについて」からバトンを引き続きます!
発注側が制作に関わるって何。
実際問題言いたいことは凄くシンプルです。なぜなら、ウェブサイトの制作にのオーナーサイドにも今までのワークフローより深く協力してもらう。というだけなのです。
concrete5案件の多い会社さんは似たようなことをやっているかもしれないけれども・・・。
小規模にはじめるウェブサイトなら、もしかしたら発注側が原稿を入れていくのも良いのではないでしょうか。
とはいえ、弊社では毎回こんな感じでやっているわけではないということも合わせて書いておきます。
concrete5を導入するなら、サイト制作に関わってみましょうよ。という話。
一般的なWEBサイトの制作フローはこちら。
- どんなサイトにしたいか、どんな方向性がおすすめか、などのディスカッション。
- 見積もりやラフ案などを見て検討。および発注。
- 原稿の手配。
- ページのデザインカンプなどを見て確認。
- HTMLやCSSなどのコーディング。
- CMS組み込みおよびデータ入力。
- 納品
そして、今回ご提案するのはこちら。
- どんなサイトにしたいか、どんな方向性がおすすめか、などのディスカッション。
- 見積もりやラフ案などを見て検討。および発注。
- ページのデザインカンプなどを見て確認。
- HTMLやCSSなどのコーディング。
- 最低限のCMS組み込み。
- 講習を行い、クライアント側で、実際の操作を覚えつつデータ入力を行いなう。
- もともと想定していなかった運用における要望や対応策の協議などを含め、追加予算の再見積もり。
- 追加があれば、追加機能の制作。同時進行で細かい調整を進める。
- 納品
とまあこんな具合にしてみたら如何でしょう?というお話です。
いろいろ気をつけるべきポイントもあるのですが、こんな感じのワークフローにすると、いいことも悪いこともあるよねというお話。
直感的な入力は、データ流し込みの効率化に繋がる
同業のWEB制作界隈の皆さんは、何度も経験しているであろう、納品直前の必死のデータ流し込み。
データの流し込みを制作サイドがやるということは、往々にして当然ではあるのですが、もしかしたら関係者全員がもっと幸せになる方法があるんじゃないかなと思っています。
基本的なテンプレートや機能ができた段階で、使い方のトレーニングと検収を兼ねて、原稿をある程度、サイトオーナーに行っていただくことで、そりゃあその工数削減できて制作費から削減できますよね。という話。
しかも使い方を覚えることもできるので、一石二鳥なんじゃないかという説。
とはいえ、既存コンテンツの流し込みとかなら、別の方法が良いと思いますがね・・・。
メリット
- どんな形でレイアウトしていきたいのか、その基本形を見ることで、CSSの追加などで整えることができる。
- 運用に移る前の段階で、concrete5に馴染むことができる。
デメリット
- ある程度、どんなことがしたいのかの想定ができていないとうまくいかない。
- 想定外のやりたいことがあった場合、別途専用ブロックやテンプレートを制作する必要がある。
込み入った機能の追加を検討する余地が生まれる
ブロック開発なんかでありがちだと思うのですが、その見た目をいい感じの入力で作る便利なブロック。
果たしてすべてが絶対必要なのでしょうか。
確かに、大概の場合において、専用ブロックってあったほうが便利なことは多いと思います。ただし増やし過ぎるともう管理するのが大変になってしまうわけですが。
「作らないと実現が厳しいです!」以外の部分は、実際の制作の前に、基本機能で触ってみて、「ああ、このままでもいけるね」となれば、そこは開発しなくても良いのです。
逆に、いらないと思ってたけど、やっぱりこうなっていたほうが何かと楽だよね。作るとしたらおいくら万円?といった話もできるのではないでしょうか。
「やっぱりここは必要だよね!」となれば、当然制作するわけですが、「作っておいたほうが良いですよ!」レベルのものはもしかしたら予算を圧迫するだけかもしれません。
メリット
- かけないで良い可能性のある予算について、様子を見ることができる。
- 実際の運用を想定した操作を、実践的に公開前に行うことで、運用時の注意点なども体験できる。
デメリット
- 最初の段階で、最低金額はわかるものの、最終的な予算がわからない。
- ほぼ必須だろうというところと、あったほうが良いものとの見極めに失敗をするといたずらに時間を消費する。
運用フェーズに入ってからの安定感
ウェブサイトの納品が行われ、さあ運用だ!となった場合、多くの場合マニュアル化された更新方法についての説明書が用意されることでしょう。
ただし、マニュアル化できるものというものは得てして、イレギュラーな更新対応に対応しにくいものです。
ここにこれを入力すれば、ここが更新される。ここにチェックを入れた場合こうなる。などなど。
しかし、concrete5は、レイアウトも含め、相当のことが管理画面上でできてしまいます。
そうなった場合、すべてのマニュアル化は難しいものとなることがあるでしょう。
この場合、マニュアルだけ渡されて、はい納品です!公開しますね!と、次の瞬間から運用に入ることになります。
もし、制作時からconcrete5の操作をしていれば、制作のタイミングから「これはどうすれば良いのか」などを聞くことができます。
これは、教習所にきちんと通ってから免許をとったほうが安心だよね!ということに近いのではないでしょうか。
メリット
- 公開した時にはすでに操作の基本が身についている。
- 制作サイドと、通常よりも細かいコミュニケーションがとれる。
- そもそもマニュアルなしなら価格も下がるかもしれない。
デメリット
- 入力や制作がすべて同時進行のため、専用マニュアルが公開に間に合わなくなる可能性が高い。
そんなわけでまとめ
制作フェーズで、制作会社だけではなく、クライアントもCMS操作という形で、制作の一部に関わることにより、得られるメリットもあるよね。というお話でした。
ぶっちゃけて言えば、どのCMSも同じようにできる可能性はあります。
ただし、コンクリはこの方法論と非常に相性が良いのではないかなーと思っています。
最後に、全体を通したメリット・デメリットをまとめたいと思います。
状況によって、変わるとは思いますが、CMS選定の参考になればと思います。
メリット
- 少なくとも、データ入力費用は浮く。
- 機能として要不要かどうかを、検証する時間が得られる。
- 操作を覚えた状態で納品・公開される。
デメリット
- 慣れない作業での実作業時間が発生する。
- 通常よりも時間がかかる可能性がある。
- 納品後にも追加機能が欲しくなるかもしれない。
2015年、わたしのコンクリ総括
せっかくのAdvent Calendarなので、まとめてみようかなあと思います。
2015年は、東京UGの一員として、秋のオープンソースカンファレンスへの参加や、勉強会で登壇させていただく機会をいただくなど、充実したコンクリライフを送らせていただきました!
実際に制作したウェブサイト自体は数件ではありますが、メンテナンス含め、concrete5に関われるウェブサイトが増えてきて嬉しい限りです。
来年はもうちょっと色々やりたいなあと思っています。
さて、明日の更新は、弊社で僕と一緒に取締役をやっている山崎さんの予定です。
山崎さんと、うちの代表の多生さんが書けば、弊社取締役全員がこのAdvent Calendar参加ですね!やったね!